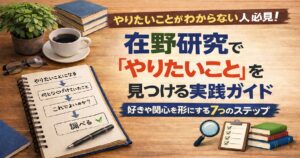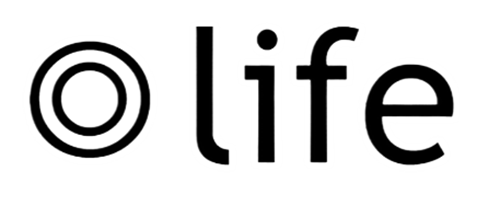紙とペンだけで、話の内容をスピーディーに書き取れたら――
そんな力を身につけたいと思ったことはありませんか?
会議や授業のメモ取りに苦労した経験がある方も多いでしょう。スマホやタブレットの音声入力が身近になった今でも、「自分の手で、必要な情報をすばやく記録する力」は変わらず役立つスキルです。
その力を支えるのが「速記(そっき)」です。
速記とは、話される言葉を素早く・正確に記録するための技術で、古代から続く歴史あるスキルです。かつては議会や裁判、新聞記者などの現場でも活躍してきました。本記事は、そんな速記の魅力と実用性をわかりやすく解説する初心者向けの入門ガイドです。
このガイドでは以下の内容をカバーします。
- 速記とは何か?種類と歴史
- 速記のメリット・デメリット
- 初心者からの基本・学び方・実践ポイント
- 表現方法としての速記
速記は学習に時間がかかりますが、習得することで得られるメリットは非常に大きいです。
ぜひこの記事を通じて、速記の魅力とその実用性について理解を深め、自分のスキルアップに役立ててください。
速記とは
速記は、演説や談話を聞くと同時に高速でメモを取り、後に普通文字に書き直す作業です。
言葉を短縮し、特定の記号やシンボルを使って情報を記録します。
速記後に文字化する技術も重要です。
これらにより話者の話す内容を、ほぼリアルタイムで書き留めることができます。
速記をマスターするまでの時間は個人差がありますが、基本的な技術を習得するのに数週間から数ヶ月程度が一般的です。
また、正確に運用することになると、外国語の学習に匹敵する教育が必要です。
運用にあたっては、速記機やテープレコーダーを記録の補助として使用します。
速記後の文字化には、欧米では主にタイプライタ―が使用され、日本ではワープロが使用されます。
速記の歴史
速記は古代から存在しており、その歴史は古代ギリシャ・ローマにまで遡ります。西洋では、ラテン語のティロ式速記や、近代になるとブライト、ウィリス、ピットマンなどの方式が発展しました。
日本では、明治維新後に田鎖綱紀がピットマン系の速記を導入し、1882年に講習会を開いて実用化しました。現在も速記方式の改良が続き、法廷や議会、新聞社などで利用されています。
速記の種類
現在、速記方式は各国で改良が続けられ、様々な種類が存在します。代表的なものには、ピットマン方式やグレッグ方式があります。
ピットマン方式は比較的直系の発展を遂げた方法であり、一方、グレッグ方式は複数の方法が融合して発展したものです。それぞれが独自の記号体系とルールを持っています。
日本では、ピットマン系を基にした田鎖式をもとに、中根式、早稲田式、衆議院式、参議院式など多様な方式が発表されています。
方式が多いのは、海外の方式を日本語に応用させるための試行錯誤の結果です。そのため、それぞれに特徴があります。
速記のメリットとデメリット
- 速記のメリット
- 話された内容を素早く正確に記録できる:会議や講義などのリアルタイムの場面で活用すれば、重要な情報の取りこぼしを防ぐことができます。さらに、速記を学ぶ過程で「聞く力」や「要点を整理する力」も自然と身につきます。
- 能力開発:見返しの繰り返しによって、記憶の定着にもつながります。また、速記を練習する中で、集中力や観察力、さらには文章表現の力も鍛えられるため、能力開発の一環として取り組むのもおすすめです。
- 応用ができる:初心者にとっても、速記は一部の専門家だけの技術ではありません。基本的なルールさえ覚えれば、日常のメモや学習ノート作成にも十分に活かすことができます。
- 社会での信用:速記を習得すれば、議事録作成や取材、文字起こしなどの仕事でも重宝され、専門的なスキルとして評価されることもあります。
「記録のプロ」を目指す第一歩としても、速記は非常に有効なスキルです。
- 速記のデメリット
- 習得に時間がかかる:速記は独自の記号や省略ルールを覚える必要があり、基礎の習得や練習にある程度の時間と努力が必要です。
- 読み書き両方の練習が必要:自分で速記を書けるだけでなく、それを後で正しく読み取れるようになるまでには、繰り返しのトレーニングが求められます。
- 使いこなすには継続的な練習が必要:一度覚えただけでは忘れてしまいやすく、実践的に使いこなすには継続的な練習が欠かせません。
- 電子機器の普及による需要の減少:スマートフォンやタブレットによる録音・音声入力が一般化しており、速記を使う場面が限られてきているのも現状です。
速記の基本技術
速記には、ただ速く書くだけでなく、情報を整理し、あとから読み返せる形に整えるための基本ルールがあります。
そのために、レイアウトと階層構造を整えながら、速記符号・省略文字・記号やシンボルを活用します。
そして、書いた速記文を普通の文章として読み直せるようにする「反訳」という作業も欠かせません。
- レイアウトと階層構造:速記のノートは、情報を効果的に整理するためにレイアウトや構造が重要です。
ノートのページを適切にセクション分けし、大見出しや小見出し、箇条書きなどを活用して階層構造を作ります。これにより、情報の関連性が明確になり、後から見返すときに理解しやすくなります。 - 速記符号:基本文字である五十音(清音)に準拠して考案され、かなり簡略化されています。
濁音・半濁音・長音・拗音・助詞にも対応しています。
これらによりスピードアップが図れます。 - 省略文字の使用: もっと早く書くために、言葉やフレーズを短縮した形に変換することで、記録の効率を高めます。
例えば、「アメリカ」を「ア」と表現するなどです。他にも、基本文字の符号や日本語で頻出する単語を省略したりします。 - 記号やシンボルの活用:特定の意味を持つ記号やシンボルを使って、情報を表現します。
例えば、「・」を「点」と表現するなどです。 - 反訳:速記で書かれた文は、そのままでは暗号に近いです。
反訳は、それを解読し、普通の文として読めるように文章を書き直す作業になります。
学習方法
マンツーマンという方法も有りかもしれませんが、初心者はこの2つの学習方法が王道です。
- 独学:独学で速記を学ぶには、専門書やオンラインを活用すると良いでしょう。
基礎的な記号やルールを覚えたら、実際に書いてみることが大切です。 - 専門学校や講座の活用:より速記を体系的に学びたい場合は、専門学校や速記講座に参加するのがおすすめです。プロの指導を受けることで、効率よく習得できます。
速記の実践ポイント
- 速記に必要な道具:基本的には、速記用のノートとペンが必要です。
速記用のノートは罫線が入っており、記号やシンボルを書き込みやすいようになっています。
また、ペンは滑らかに書けるものが好まれますが、個人の好みによって異なります。 - 練習方法:速記は習得に多くの時間を使った練習が必要です。
定期的に練習を行い、シンボルや記号の使い方を習得しましょう。
日常のメモ取りや、ニュースを速記で書き取るなど、実際に手を動かすことが上達の鍵です。 - ノートの取り方:速記を行う際には、適切なノートの取り方が重要です。
縦書きや横書き、または特定のフォーマットを使うことで、情報を整理しやすくなります。
また、スペースを効果的に活用することで、後で情報を振り返りやすくなります。 - 聴講時の注意点:速記を行う際には、話者のスピードや内容に集中する必要があります。
耳を澄ませ、重要なポイントやキーワードを見逃さないように注意しましょう。
話者のペースに合わせて迅速にに書き留めます。
表現方法としての速記
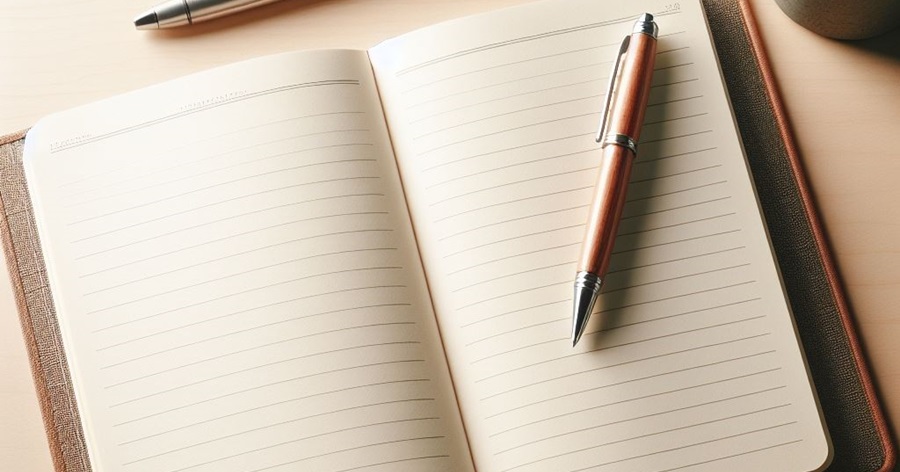
人は様々な方法で自己表現を行います。
表現方法には記事や写真、物作りなどがありますが、その中の一つが速記です。
速記は、発言をリアルタイムで書き留める技術です。
以下に活用例と、少し変わった表現方法として「自分の思考の抽出」について解説します。
活用例
速記は発言をリアルタイムに書き留めることができるため、公的な記録や講義・セミナーのメモ、会議や打ち合わせのメモ作成に非常に役立ちます。
自分の思考の抽出
人間の思考は非常に速く進み、そのすべてを自然言語で記述するのは非常に難しいです。
さらに、人は今この瞬間に考えていたこともすぐに忘れて、次の思考に移ります。
また、一日に無数の選択を行います。
速記を使うことで、このような思考の内容をある程度抽出することが可能です。
瞬時に思いついたことや考えを速記で素早く記録することで、後から見返して整理したり、新たなアイデアを生み出したりするのに役立ちます。
下記がその例です。
- 生活メモやToDoリスト
- 各種情報の記録や整理
- アイデアや思考の整理
- 草稿作成
- 学習の補助
このように、速記はただ情報を記録するだけでなく、自分の思考を効果的に整理するツールとしても活用できます。
速記を仕事にしている主な職種
以下のようなものがあります。
法廷速記官、国会速記者、会議・株式総会での速記者、教育機関での速記教師などです。
会議の議事録作成、法廷での証言記録、ジャーナリストのインタビューなど、様々な仕事があります。
Q&A
まとめ
速記は、情報を素早く正確に記録するための重要な技術です。
その歴史は古代ギリシャ・ローマに始まり、現代に至るまで様々な方式が発展してきました。
速記を学ぶことで、会議や講義の内容をリアルタイムで記録でき、専門的な職業スキルとしても評価されます。
しかし、電子機器の普及や学習に時間がかかることから、現在ではあまりメジャーではありません。
速記の基本技術には、速記符号の使用、省略文字の活用、記号やシンボルの活用などがあります。
これらをマスターすることで、より効率的に情報を記録することが可能になります。
また、速記を学ぶためには独学だけでなく、専門学校や講座の活用もおすすめです。
当記事をきっかけにして、まずは速記について知り、実際に手を動かして練習してみましょう。
独学や講座の選択肢も検討し、自分に合った方法で速記スキルを磨いてください。
速記を習得することで、情報の記録や整理が効率的に行えるようになり、日常生活や仕事の効率が向上します。
また、自分の思考を抽出するといった自己啓発的な活用も期待できます。