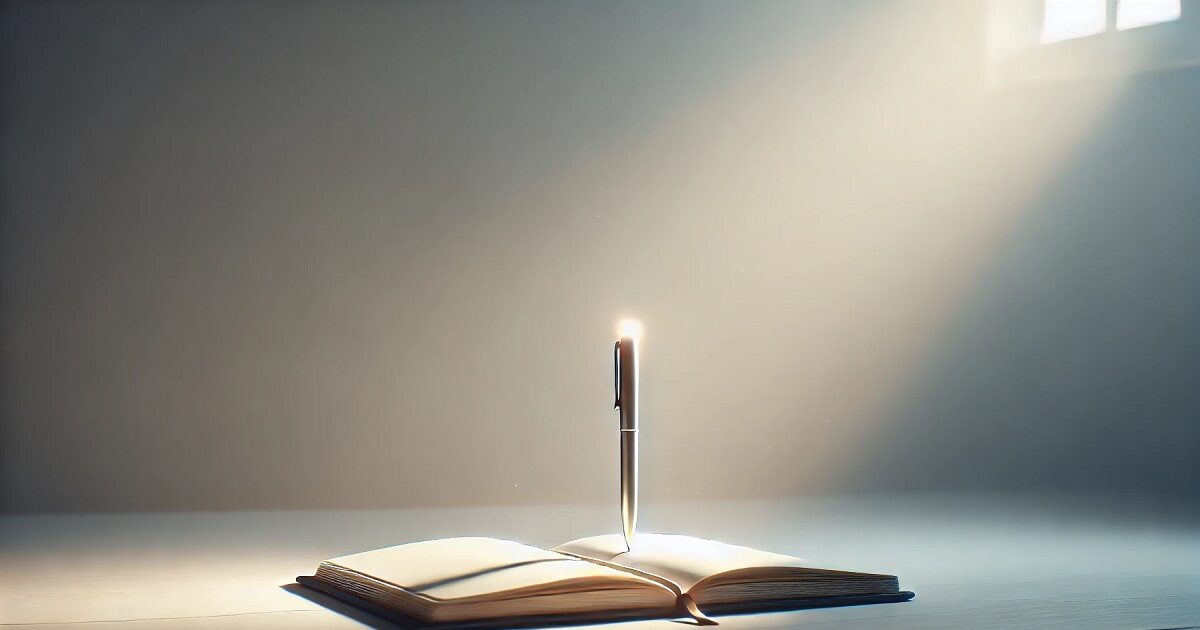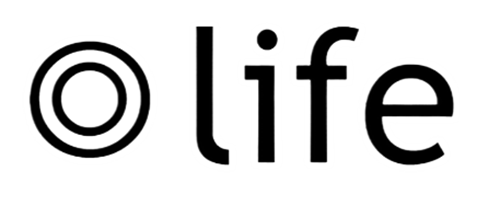誰しも、自分らしさをどう表現するかに悩んだことがあるでしょう。日々の生活の中で、自分の内なる声をどう形にすれば良いのかと考えたことはありませんか?
そんなあなたにとって、読書がその鍵となるかもしれません。
自己表現を豊かにするためのヒントはどこにあるのでしょうか?
「自己表現を高めたいけれど、どこから始めればいいのかわからない」と感じている人は多いはずです。表現力や感性を育てる方法を見つけるのは簡単ではありません。
そんな悩みを解決する手段として、読書は非常に効果的です。本記事では、読書が自己表現の基盤をどう築くのかを詳しく解説します。読書を通じて得られる新しい視点や感情が、自己表現の力をどのように高めるかを探り、具体的な読書の楽しみ方や実践方法もご紹介します。
本記事を読むことで、自己表現を豊かにするための具体的な読書方法を知ることができます。日常に取り入れやすい実践的なアプローチを通じて、自分らしさを効果的に表現する力を養うことができるでしょう。
自己表現に迷っているなら、まず読書を始めてみましょう。日常に読書を取り入れることで、心が豊かになり、自然と自己表現の道が見えてくるはずです。
読書が新たな可能性を引き出すきっかけになるでしょう。
- 読書について
- 自己表現とは何か
- 読書と自己表現の関係
- 読書法と読書感想のやり方
読書について
読書は、知識の吸収だけでなく、感情や思考を豊かにし、自己成長を促進するための重要な行為です。
読書によって、他者の経験や価値観に触れることで、自分の視野を広げ、新しい視点を得ることができます。
物語や知識を取り入れることは、日常生活に豊かさと深みをもたらします。
また、読書は語彙力や表現力の向上にもつながり、自分の考えや感情を的確に言語化する力を養います。
これは、自分に適した自己表現の方法を見つけるうえで、極めて有効です。
自己表現とは
自己表現とは、好きなこと、興味や好み、感情、理想などの自己の内面を、言葉や行動、立体物などを通じて表すことです。その手段は多岐にわたり、趣味、アート、文章、会話、活動、スポーツ、モノづくり、さらにはボディランゲージやファッションなど、さまざまな形で現れます。
こうした自己表現を通じて、自分の考えや感情を整理し、他者に伝えることができるようになると、ストレスの無いコミュニケーションが可能になり、人間関係も良好になります。さらに、これは社会への働きかけにつながり、やりたいことを見つけるきっかけにもなります。
読書と 自己表現について
読書と 自己表現の関係を「自己表現を高めるための読書の役割」や「自己表現から見た本の各ジャンル」で見ていきます。
自己表現を高めるための読書の役割
読書を通じて得た知識や感情は、自己表現の重要な材料となります。
- 物語の登場人物に共感することで、自分の気持ちに気づき、それをうまく伝える力が少しずつ育っていきます。
- 言葉の使い方や表現にふれることで、自分の思いをもっと豊かに伝えられるようになります。
- 絵やものづくりなど、さまざまな表現の方法があることに気づけて、新しいアイデアを思いつくきっかけにもなります。
自己表現から見た本の各ジャンル
書籍には様々なジャンルがあります。
| メインジャンル | サブジャンル |
|---|---|
| フィクション(文学・小説・漫画) | 一般小説、ミステリー、SF・ファンタジー、ロマンス、歴史小説、サスペンス、詩)※詩は異論があるかもしれません。 |
| ノンフィクション | エッセイ、自伝・伝記、歴史・政治、科学・自然、ビジネス・経済、心理学、自己啓発 |
| 参考図書 | 辞書・百科事典、マニュアル・ハンドブック、習い事などの教書 |
| 芸術・美術 | 絵画・彫刻、音楽、演劇・映画 |
| 宗教・哲学 | 宗教書、哲学書 |
| 子供向け | 絵本、幼児向け図書、ヤングアダルト小説 |
| 学術図書 | 専門分野の教科書、研究書・論文集 |
| 新聞・雑誌 | 日刊紙、週刊誌、専門誌 |
自己表現から見た各ジャンルは下記のようになります。
ジャンル選びの参考にしてください。
| ジャンル | 得られるもの | 詳細 |
|---|---|---|
| フィクション | 想像力 | 小説や物語などは、人の気持ちや心の動きを知るのにとてもよい本です。登場人物の気持ちに共感したり、自分と重ね合わせたりすることで、自分の心についても少しずつわかるようになります。 また、自分とは違う世界の物語を読むことで、いろいろな見方や考え方が分かり、自分の表現の幅を広げるために役立ちます。 |
| ノンフィクション | 学び | ノンフィクションは、実際にあったことや本当の話にもとづいた本です。自己啓発、伝記、エッセイなどを読むことで、人の体験や大切な教えを知ることができます。そうした本から学んだことは、自分の考えや気持ちを表すヒントにもなります。 現実の出来事を通して、自分の考え方や大事にしていることを見直し、それを人に伝える力を育てることができます。 |
| 参考図書 | 知識とスキル | 参考図書は、知識をわかりやすく整理したり、何かを学ぶときに役立つ本です。辞書や百科事典は、言葉の意味や事実を調べるときに使える、信頼できる情報がのっています。そうした本を使うことで、自分の考えを人に伝えるときに、正しい言葉や説得力のある表現ができるようになります。 また、マニュアルやハンドブックのような本は、やり方をわかりやすく説明してくれるので、実際に何かを練習したり上達したいときに便利です。習い事のテキストや教本も、趣味や専門分野の知識を深めたり、自分の表現の幅を広げるために役立ちます。 |
| 芸術・美術 | インスピレーション | 芸術や美術に関する本は、絵や彫刻、音楽、演劇や映画などについて知ることができる本です。こうした本を読むと、創造力が刺激され、自分の感性も育っていきます。 芸術についての知識が深まると、自分の表現にも活かせるようになります。たとえば、色づかいや音のイメージ、動きや演出など、いろいろな形で表現に取り入れることができるようになります。 |
| 宗教・哲学 | 深い思索 | 宗教や哲学に関する本は、人の心や生き方、善悪について深く考えるきっかけを与えてくれます。こうした本を読むことで、自分の考えや価値観を見つめ直し、人生や自分自身について考えるようになります。 宗教の本は、目に見えないものや心のあり方についてスピリチュアルな視点から考える手助けをしてくれます。 一方、哲学の本は、物事を筋道立てて深く考える方法を教えてくれます。 どちらの本も、自分の表現に「意味」や「想い」を込めるヒントになります。 |
| 子供向け | 豊かな想像力 | 子供向けの書籍は、成長期の想像力や感性を育む重要な媒体です。これらの書籍は、シンプルで理解しやすいストーリーやイラストを通じて、子供たちの創造力や共感力を刺激します。 また、ヤングアダルト小説は、若い読者が自己を見つめ、他者との関係性を築く上での影響を与えます。子供の頃に培った想像力や感受性は、大人になってからの自己表現にも影響を与え続けます。 |
| 学術図書 | 専門知識 | 学術図書は、ある分野について深く学ぶための本です。専門書や研究の本を読むことで、物事を分析したり、筋道を立てて考えたりする力が身につきます。これによって、難しいテーマについてもしっかり理解できるようになります。 こうした専門的な知識は、自分自身の意見を伝えるときにも役に立ちます。説得力のある言い方ができるようになったり、専門的な場面でも自信を持って発言できるようになります。 また、自分の考えにしっかりとした根拠を持たせることで、表現をより確かなものにしてくれます。 |
| 新聞・雑誌 | 最新情報 | 新聞や雑誌は、今のニュースや話題、いろいろな分野の情報を知るのに役立つ読みものです。 毎日出る新聞や週刊誌では、社会で今起きていることや、気になる問題についての情報を得ることができます。 そうした情報を知ることで、今の社会に合った発言ができるようになります。 また、月刊専門誌などは特定の分野に特化した情報を提供し、自分の興味や関心に関連する知識を深めるのに役立ちます。 |
読書をする
読書には多くの技法があり、それを使いこなすことで、知識を深められます。しかし、最初は難しく考えずに、できるだけ多くの本を普通に読むことをお勧めします。下記は多読と読書の各ポイント、取り入れたい読書技法、読書感想の流れを解説します。
読書の流れ
多読を選択
基本的な読み方は、全体の理解を意識しつつも、内容が完全に理解できない場合でも、そのまま読み進めます。読み終えたら次の本を読みます。同時に数冊を並行して読んでいく方法もあります。その時に理解できない場合でも、そのまま読み進めます。
読書の準備
今から読む1冊あればよいのですが、準備しておけば2冊目以降楽に進みます。
何を読むか?
読書は「何を読むか」で始まります。しかし。多くの本があり、どれを読めば良いか迷ってしまいます。
そのためか、現代では最も効果的な本を選ぶことがもてはやされてもいます。理由は「人生を変えた本」が存在するからだと思います。
しかしながら、実際に大量の本の中から「効果的な本」ような本を見つけ出すのは難しいです。なぜなら「人生を変えた本」は後になって初めて分かるものだからです。したがって、興味のあるテーマを選んで読み始め、それをきっかけにして他のジャンルを読むのが妥当かもしれません。
興味のあるテーマを選ぶ
自分が興味を持っているテーマや突き詰めたいジャンルにもとづいて本を選ぶと、より読書への意欲が高まります。自分のことに関係ある内容の本なら楽に読めると思います。
読書の環境を整える
静かで集中できる環境を整え、読書に没頭できる時間を確保しましょう。たまには、図書館にいくのもよいでしょう。絶版などの本が有るかもしれません。
読みたい本リストを作る
気になる興味ある本をリストアップし、順番に読んでいくことで、読書の楽しみを維持できます。また迷った時は、ベストセラーを読むという選択肢もあります。みんなが読んでいるということで、世の中とのつながりを感じることができるかもしれません。
理解を自然に待つ
読書の内容の理解は自然に任せましょう。自分のペースで進め、分からない部分があってもイライラせずに読み続けることが大切です。無理をしても分からないものは分からないので、焦らずに自然の流れに任せることが必要です。
そして、読書を続ける中で、理解できなかった部分の「答え」が突然得られる瞬間があります。「あっ!そういうことか!」と思わず心の中で声を上げるような気付きの瞬間です。これは、よく言われる「点と点がつながる」という経験に似ています。生理的な感覚と言っていいほどです。
この「気づき」は、新しい知識にたどり着いた証であり、新たな視点を得たことでもあります。
気づきを通して、考え方や判断の幅が広がり、物事をより高い視点から俯瞰できるようもなります。
こうした気づきは、自己表現の土台となるだけでなく、「自分は何をやりたいのか」といった人生の方向性を見つける手がかりにもなるでしょう。
多読の効果の実感
このように、いろいろなジャンルの本を読んでいくと、さまざまな考え方や見方にふれることができます。すると、前に読んだときはよくわからなかった本の内容が、あとになって少しずつ分かってきます。
たとえば、最初に読んだAという本は、30%くらいしか分からなかったとします。でも、そのあとにBやCという本を読んだことで、「あ、あのときの話はこういう意味だったのか」と気づいて、Aの内容がもっと分かるようになることです。
このように、いろいろな本を読むうちに、少しずつ理解が深まり、前に難しいと感じた本でも、あとから読んで納得できるようになることがあります。
読書の習慣化
読書はいかに習慣化させるかが重要です。習慣化の方法を試みて、「読書しない自分はありえない」と思えてしまうなら習慣化したといえるでしょう。以下が、読書の習慣化の3つの工夫です。
生活に無理なく取り入れる方法
- 文庫本一冊を持ち歩き:どこへ行くにも文庫本一冊を持ち歩き、少しずつ読む。移動中や待ち時間を活用し、気軽に読書を楽しむことができます。
- 積読: 本を見えるところに置き、読む気を誘う。
視界に本があることで、自然と読書への意欲が高まります。 - 風呂やトイレを読書空間にする:リラックスできる空間で読書を楽しむことで、負担なく本の内容に集中できます。
- スキマ時間を使う:通勤時間や待ち時間を有効活用し、短時間でも継続的に読書を行います。
時には、意地でも分厚い500ページの本を読むことも挑戦してみましょう。
ただし、これは読書が苦痛になってしまう可能性があるため、特に自分にとって関心のない内容や興味のない本は避けたほうがよいかもしれません。
しかし、「毒薬変じて薬となる」ということわざがあるように、挑戦する価値はあります。
なぜなら、困難な本を読み切ることで得られる妙な自信が、次への意欲を高め、読書習慣を身につけるきっかけになることがあるからです。
習慣のマジックナンバー4
巷には「100日英語」や「100日〇〇」「3か月〇〇」といったタイトルの本が多く見られます。
基礎を学ぶために必要な期間として100日前後が選ばれているのかもしれません。
実際に、これに近い考え方として「習慣のマジックナンバー4」があります。
これは、やりたいことを「週4回以上のペースで8週間続ける」と習慣化しやすいというものです。
週4回以上のペースとは、例えば、120分の筋トレを60分×2日行うよりも、30分×4日の方が効果的であるという考え方です。
ロンドン大学が96人の学生を対象に行った調査では、様々な行動を設定した結果、50~60日でその行動が習慣化しやすいことが分かりました。
これを読書にも応用すると、「習慣のマジックナンバー4」に従って56日以上続けることで、読書が習慣化する可能性が高まります。
具体的には、例えば、週20分×4日の読書時間や、空いた時間を利用して毎日12分間程度の読書を8週間続けることが挙げられます。
if-then プランニング
if-then プランニングは、自動的に行動を習慣化させるための手法です。
自分自身に「もし〜ならば、私は〜をする」というルールを設定することで、行動の動機付けを行います。具体的な行動計画を立てることで、目標達成への道筋が明確になり、自己効力感を高める効果があります。読書時間の確保にも非常に有効なテクニックです。
- 例1:用事が済んで車の座席に座ったら、一息つく5分間の読書をする。これは一日に何回か繰り返すことができます。
- 例2:朝、昼、夕方、就寝前など、決まった時間に読書する。
他の技法
読書をしていき、さらにより効果を上げるために様々な読み方を試してみましょう。読書には、さまざまな読み方のスタイルがあります。
以下はその一部です。
| 読み方 | 特徴 |
|---|---|
| 黙読 | 声に出さずに読むこと。集中して読む際に適しています。現代人ではあたり前の読み方です。 |
| 通読 | 始めから終わりまで読み通すこと。全体像を把握するための読み方です。 |
| 熟読 | じっくりと内容を噛み締めながら読むこと。深い理解を得たい時に適しています。 |
| 速読 | 短時間で多くの情報を把握する読み方。読書していくに従って身につくスキルといえます。技術としてありますが、何も分からない本をいきなり読んで理解するといったスキルではないです。 |
| 再読 | 同じ本を何度も読むこと。理解を深め、記憶に定着させるために有効です。 |
| 積読 | 本を読むことなく積んでおく状態。後で必要な時に参照できるため、無駄ではありません。しかし、「読まないと」というストレスが溜まったり、本の保管場所が必要になってきます。 |
| 素読 | 声に出して読むこと。文章のリズムや構造を体感することができます。歴史的には記憶やリズムを重視して教育に用いられました。現代でも、音読することで内容の理解や記憶の定着に役立ちます。内容の理解が必ずしも求められない段階でも、反復して音読することで、次第に内容が自然に理解できるようになるとされています。 |
以上が読書の流れです。
アウトプット
読書して感想述べることは、自己表現にもなります。読書感想は表現方法の一つです。
書くこと
読書感想文を書くことで、読んだ内容を自分なりに整理し、他者に伝える力を養うことができます。感想文では、単なるあらすじではなく、自分が感じたことや考えたことを中心に書くことが重要です。具体的な例や引用を使いながら、どのように感じたか、どう自分に影響を与えたかを表現してみましょう。
読書会やオンラインディスカッションへの参加
読書を通じた自己表現をさらに深めるためには、読書会やオンライン上のディスカッションに参加することも効果的です。他者の意見や感想を聞くことで、自分の考えを客観的に見直すことができ、新たな視点を得ることができます。
また、自分の意見を発表することで、言葉での表現力やコミュニケーション能力を高めることができます。
Q&A
まとめ
読書は自己表現の土台を築く上で欠かせない要素です。
フィクションやノンフィクション、詩やエッセイなど、さまざまなジャンルの本を読むことで、自分自身の感情や思考を深く理解し、表現する力を育むことができます。
また、好きなことや、やりたいことに気づくきっかけにもなります。日々の読書習慣を取り入れ、読書感想文を書いたり、読書会に参加するなどの実践方法を取り入れて、自分らしい自己表現を追求してみましょう。
参考書籍
短期間で“よい習慣”が身につき、人生が思い通りになる! 超習慣術 メンタリストDaiGo著