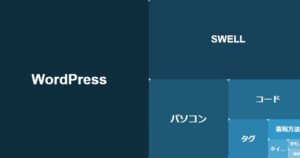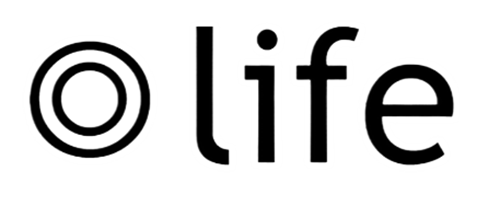ビットコインとは、分散型のコンピュータネットワークと暗号技術によって管理され、通貨としての機能を持つデジタルデータです。その仕組みは中央の銀行や管理者に依存せず、世界中の参加者によって維持されています。そのため多くの人々が投資対象や技術的な革新として注目しています。
では、そんなビットコインを「趣味」として始める魅力はどこにあるのでしょうか?
- 新しいテクノロジーに触れる体験
- 通貨としての可能性を学ぶ楽しみ
- ビットコインを保有する者同士が交流するコミュニティへの参加
このように、ビットコインは投資だけでなく「学び」や「交流」といった要素を持つ点が、趣味としても魅力的なのです。
本記事では、ビットコインを趣味として始める魅力について語り、その基礎知識から始める手順、さらには趣味としての方法までを解説します。
手順
- 簡単なビットコインの基本知識
- 取引所で口座を開設し、ビットコイン購入の解説
- 趣味としてのビットコインの紹介
では、始めていきましょう。
※総称について
仮想通貨は、暗号通貨、暗号資産、クリプトといろいろな言われ方をされています。本記事では、基本的に「暗号通貨」と表記します。場合によっては、「暗号資産」と表記します。
- ビットコインを趣味として始めるのに魅力的な理由
- ビットコインの始まりと、安全性と分散化の特性について
- 取引所で口座を開設し、ビットコインを購入する手順
- 趣味としてなら、どのように取引(トランザクション)をしていくか
- ビットコインの楽しみ方
ビットコインを趣味として始めるのに魅力的な理由
ビットコインを趣味として始める魅力的な理由として、「ビットコインの人気と普及、投資としての魅力、技術としての興味、世界観」の4つが挙げられます。
ビットコインの人気と普及
ビットコインは常に注目を集めており、その普及も進んでいます。新聞やメディア、SNSなどでビットコインに関する情報が溢れており、人々の関心を引きつけています。
このように情報も入手しやすく、購入も一般化しています。
投資としての魅力
過去の価格変動を見ると、株とは違った価値の急上昇をする場合もあります。そのため、多くの人々がビットコインを購入し、将来的な価値の上昇を期待しています。
ビットコインは投資としても魅力的です。
技術としての興味
ビットコインはブロックチェーン技術を基盤としています。
そのため、技術的興味を持つ人々にとっては、ブロックチェーンの仕組みやビットコインの動作原理を学ぶことが魅力的です。
世界観
ビットコインは、サトシ・ナカモトによるブロックチェーンの論文が公開されて以来、多くの謎を秘めています。その創始者であるサトシ・ナカモトの正体や、彼(あるいは彼ら)がどのようにしてビットコインを創造したのかという点に関しては、未だに多くの議論がなされています。
ビットコインの謎や未解決の問題に対する考察は、愛好家や研究者の間で盛んに行われています。また、ビットコインの価格変動の背後にある要因や、市場の動向を正確に予測することは容易ではありません。
ビットコインを趣味として始めることで、その謎に挑み、世界経済を予測し、新たな発見や洞察を得ることができるかもしれません。
ビットコインの基礎知識
ビットコインに興味を持ち、購入を考えるなら、まずはその仕組みや特徴を理解しておくことが大切です。
ビットコインの通貨単位は「BTC」と呼ばれ、2008年10月にサトシ・ナカモトという謎の人物(あるいはグループ)が発表した論文をもとに、2009年には実際のソフトウェアが開発・公開されました。そこから世界中に広がり、取引規模は急速に拡大していきました。
ビットコインは、ブロックチェーン・マイニング・フルノードといった仕組みによって分散的に運営されており、中央の管理者がいなくても信頼性を保つことができます。
また、個人がビットコインを利用する際には、資産を安全に保管するための「ウォレット」が必要になります。ウォレットは、ライトノードを利用したクライアントサービスとして機能し、利用者にとっての利便性を提供する仕組みです。
BTC
暗号通貨のビットコイン(Bitcoin)とは、ブロックチェーン技術を活用した最初の実例であり、「元祖」として広く知られています。
現在では、多様な暗号通貨が登場していますが、依然として最大であり基軸的役割を担っています。そして総資産量No.1です。
ビットコインは「BTC」とも呼ばれ、基盤となるのがビットコインのブロックチェーン(ビットコインチェーン)です。
他の暗号資産(トークン)をビットコインチェーンに乗せる試みはありましたが、今後もビットコインチェーン上で「独自の価値を持つ暗号資産」が出てくることはことはないでしょう。
BTCは、ビットコインの取引や価格表示にも使われる略号(シンボル)であり、株式における「銘柄コード」のような役割を果たします。取引所などでは、このシンボルによって通貨が識別され、BTC/JPYのような形式で売買が行われます。売買時の暗号資産を取引・管理には、「ウォレット」と呼ばれる保管・記録のためのツールを使用します。
こうした特徴を持つビットコインは、どのようにして生まれたのでしょうか。
では、その誕生から見ていきましょう。
誕生
ビットコインの始まりは、論文の投稿とソースコードの投稿からです。そして、本人の消息不明で終わらずに、コミュニティによって発展していきます。
論文投稿
中本哲史(Satoshi Nakamoto / サトシ・ナカモト)と名乗る人物がインターネット上に投稿した論文によって、ビットコインの概念が提唱されました。
出典:📄ビットコイン: P2P 電子通貨システム
オープンソース公開
このビットコインの理論を実現するためのオープンソースのソフトウェアがサトシ・ナカモトにより開発され、公開されました。
このソフトウェアを通じて、最初のビットコインのブロック(ジェネシスブロック)が採掘され、ビットコインのプロジェクトとブロックチェーンが開始されました。
その後も、このプロジェクトには多くの開発者が参加して、彼はこのビットコインのプロジェクトのリーダーシップを担い、プログラムの改良や開発を進めました。
※最初のブロックには、50BTCの報酬が含まれていました。
サトシ・ナカモトが消息不明になる
彼はオンライン上での活動を停止し、その正体や居場所は不明のままです。
そのため、サトシ・ナカモトの正体は未だに明らかにされていません。
その後
ビットコインコミュニティは、開発や改善のための議論を継続し、新しい機能やプロトコルの提案を行ってきました。そのため、ビットコインのプロジェクト、ブロックチェーンとその技術は、サトシ・ナカモトの不在にもかかわらず活発に進化し続けました。
このように、多くの開発者がビットコインのソフトウェアを保守し、新機能の開発やセキュリティの向上に取り組んでいます。
また、サトシ・ナカモトがビットコインのプロジェクトを離れた後も、新たなブロックチェーンプロジェクトが次々と生まれ、ブロックチェーン技術はさまざまな分野に応用されるようになりました。
その中には、イーサリアムやリップルなどの有名なプロジェクトが含まれます。
※イーサリアムやリップルなどのビットコイン以外の仮想通貨は一般的に「アルトコイン」として総称されています。
取引の歴史
取引は個人レベルから取引所を介して大規模化していきます。しかし、大規模化しても個人間の取引はなくなっていません。
黎明期
ビットコインの初期の取引は、主にコミュニティやフォーラムを通じた、個人間のP2P(ピア・ツー・ピア)取引によって行われていました。なかでも特に有名なのが、2010年にビットコインでピザが購入されたというエピソードです。
この出来事を記念して、毎年5月22日は「ビットコイン・ピザ・デー」として知られています。
このように、ビットコインの初期段階では、仲介者を介さない直接的なやりとり(P2P取引)が主流だったのです。
そのため、ビットコインの価格はまだ安定しておらず、取引所も存在していなかったことから、価格設定は主に個人の見積もりや、限られた市場における需要と供給に基づいて行われていました。
取引所誕生
しかし、ビットコインの普及と需要の増加に伴い、専門の取引所が登場しました。これらの取引所では、ビットコインを他の通貨と交換することができ、ビットコインの価格は市場によって決定されるようになりました。
最初のビットコイン取引所の一つは、2010年に設立されたMt.Goxでした。Mt.Goxは破綻してしまいましたが、その後も多くの取引所が登場し、競争が激化しました。今ではバイナンスを始め多くの取引所が存在します。
一般化
現在は、「ビットコインがもらえる」などキャンペーンもあり、かなり一般化しています。そして、個人間のは取引は現在も残っているが、主流は取引所です。
このように、通貨としての利用(決済性)よりも投資商品として扱われるのが現状です。そのため、ビットコインは比喩として、「デジタルゴールド」と言われたりもします。
ビットコインの仕組み
ビットコインの取引(トランザクション)は、中央の銀行や管理者がいません。
代わりに「ブロックチェーン」と呼ばれる台帳を、同じネットワークに参加している「マイニングノード」と「フルノード」といったコンピュータに分散させ、タイムスタンプ(=承認時刻)を付けながら、取引ごとに承認・検証 することで、分権化を実現しています。
取引(トランザクション)の発生
ビットコインの利用者が誰かに送金すると、その取引データがネットワークに流されます。この段階ではまだ承認されていない「取引メモ」のような状態です。
その後、多数のコンピュータ(ノード)に取引メモは行き渡り、まとめられ、検証され「取引の情報」になります。
ブロックチェーン
その取引のを含む複数の情報は「ブロック」という単位でまとめられます。その中身は、取引データ・前のブロックのハッシュ値・タイムスタンプ(時間の刻印)・ ナンス・このブロック自体のハッシュ値といった情報を含みます。
これらのブロックが時間順につながっていくことで鎖(チェーン)のような構造を作ります。これがブロックチェーンです。
ブロックの中身
- 取引データ(トランザクション):そのブロックにまとめられた送金記録。
- 前のブロックのハッシュ値:これが「前のブロックへのリンク」となり、鎖(チェーン)の構造を作ります。
- タイムスタンプ:ブロックが承認された時間を記録。取引の順序が時系列で固定されます。
- ナンス(Nonce):マイニングの際に必要な調整用の数値
- そのブロック自体のハッシュ値:上記4つをハッシュ関数に通すことで得られる数値。マイニングにおける「答え」になります。答えの条件に合わせるためにナンスを変更していきます。変更は答えが出るまでマシンが行います。
答えの条件:ビットコインのマイニングでは、ハッシュ値の先頭に一定数の0が並ぶような答えを見つけることが条件になっており、この0の数が「難易度」として調整されています。
難易度調整:ビットコインは 約10分に1ブロック が生成されるように設計されています。ネットワーク全体の計算力(ハッシュレート)が増えすぎると簡単に答えが出てしまうので、約2週間ごとに「難易度」が自動調整されます。これにより、世界中でどれだけマシンが増えても、平均10分に1ブロックというペースが維持されます。
P2P
通信する方式は、サーバーを介さずに コンピュータ同士が直接つながって通信する、P2P(ピア・ツー・ピア)です。したがって、ブロックチェーンは、このP2Pネットワーク上で動き、取引を記録し合い、全員で共有することで信頼性を確保しています。
この仕組みにより、ブロックチェーンは特定の場所で集中管理されるのではなく、世界中のコンピュータがそれぞれ同じ内容を保持する「分散した状態」で管理されています。
こうして、多くの参加者が同じ内容を持つことにより、記録の透明性が保たれ、不正な書き換え(改ざん)を非常に困難にします。
では、新しいブロックはどうやって作られ、「正しい」と判断されるのでしょうか?
それを担うのが「マイニング」という計算力の競争と、「フルノード」による検証です
マイニング
マイニングとは、新しいブロックを作るために、多くのコンピュータ同士がハッシュ関数による計算問題を解く競争を行うことです。
この競争は「Proof of Work(プルーフ・オブ・ワーク)」というコンセンサスアルゴリズム(取引の正しさを証明する仕組み)によって実現されており、ネットワークの分散性と耐久性を支えています。
この役割を担うコンピュータをマイニングノードと呼びます。承認に成功したマイニングノードには、報酬としてビットコインが与えられます。この作業に参加する人々はマイナー(マイニングノード所有者)と呼ばれ、報酬を受け取ります。
過程
最初に答えを出したコンピュータは、その答えが正しいとフルノードで判断されたら、ブロックを作る権利を得ます。これを「承認」といいます。その結果、ブロックが作られ、ブロックチェーンに追加されます。そして、取引の都度そういった作業が繰り返されます。
さらに、ビットコインのアルゴリズムには「最長チェーンのルール」が組み込まれています。これは、「複数のブロックが同時に作られて一時的に枝分かれが発生した場合でも、最も長く続いたチェーンこそが正しい」とみなされる という仕組みです。
このルールによって、全てのノードが自然と同じブロックチェーンに合意するようになり、分散システムにおける「集団の意思決定」が自動的に成立します。
しかし、このルールを逆手に取って「計算力の過半数を握れば、自分のチェーンを最長にできる」51%攻撃問題が出てきますが、経済的に成立しないよう設計されています。
マイニング補足
マイニングは、規模・エネルギー問題・計算力・技術的な誤解・報酬・マイナーの動向という視点で掘り下げることができます。
| 視点 | 解説 |
|---|---|
| 規模 | ビットコインが誕生した当初は、市販のパソコンでもマイニングが可能でした。しかし現在では競争が激化し、専用の高性能マシンが必要なほど規模が大きくなっています。そのため、マイニングを行っているのはほとんどが企業や事業者であり、個人で参加する場合はマイニングプールへの参加がほぼ必須です。 とはいえ、ごくまれに個人がソロマイニングで承認に成功するニュースもあり、「宝くじレベル」で小規模マイニングを確認できます。 |
| エネルギー問題 | ビットコインが誕生した当初は、市販のパソコンでもマイニングが可能でした。しかし現在では競争が激化し、専用の高性能マシンが必要なほど規模が大きくなっています。そのため、マイニングを行っているのはほとんどが企業や事業者であり、個人で参加する場合はマイニングプールへの参加がほぼ必須です。 とはいえ、ごくまれに個人がソロマイニングで承認に成功するニュースもあり、「宝くじレベル」で小規模マイニングを確認できます。 |
| 計算力 | 世界中で稼働するマイニングマシンは、1秒間に天文学的な数の計算をこなしています。単純な「ハッシュ計算数」だけで見れば、スーパーコンピュータを凌駕しています。ハッシュ計算超特化マシン群といったところです。用途は限られますが、地球上で最大規模の分散型コンピュータネットワークとも言われています。 この計算力による安全性と信頼性が、ビットコインの価値の理由の一つです。しかしながら、これを無駄という意見もあります。価値の捉え方は人それぞれです。しかし、その価値観の中で多くの人がビットコインを購入しているので、その価値は認められているのです。 |
| 誤解 | 現在新しい通貨が次々に誕生しているため、ビットコインは「古い技術」と誤解されがちですが、それは正しくありません。 なぜなら、PoWは今でも最も実績あるセキュリティモデルだからです。 また、多くの新しい通貨はソフトウェア上の仕組みに依存しているため、資産としての裏付けが弱く見られがちですが、ビットコインは 膨大な計算力と電力という現実のリソースに支えられた「現実とつながったデジタル資産」 です。 |
| マイニングの報酬 | マイナーの報酬は、新規発行されるビットコインと取引手数料で支払われます。発行上限は 2100万BTC(ただし実際に流通する量は紛失などでそれ以下)で、約4年ごとに報酬が半減する「半減期」も設定されています。 すべての発行は およそ2140年頃に終了し、その後は取引手数料のみがマイナーの報酬源となります。 もっとも、その時代にマイナーが十分にネットワークを維持できるかどうかは、まだ確定していません。 ただし、もしビットコインが世界的に利用され続けていれば、取引量や手数料も増加し、手数料だけでも十分な報酬になる可能性があります。逆に需要が減れば、マイニングの仕組み自体を見直す議論が行われるかもしれません。こうした将来のあり方については、すでにコミュニティで議論が続けられています。 |
| マイナー | BTC価格、マイナー数、計算力(ハッシュレート)は連動しています。価格が高騰すればマイナーが増え、計算力が上がり、安全性も増します。逆に価格が下落すればマイナーが撤退し、計算力が低下するリスクもあります。 |
フルノード
フルノードは、受け取ったブロックや取引がルール通りに作られているかどうかを検証する役割を担います。
たとえば、
- 不正な署名がある
- 報酬の取りすぎ
- ブロックサイズの超過
といった明らかなルール違反はフルノードによって即座に弾かれます。
また、このフルノードは「世界中のネットワーク参加者に同じ内容として共有・保存」を実現する役割も担っています。マイニングノードがブロックを作り、フルノードがそれを検証する。この二重の仕組みによって、不正は非常に困難になります。
フルノードは、高速化が著しいマイニングマシンによるマイニングノードとは違い、一般的なパソコンでも構築可能です。そして、その環境を用意できれば誰でも「取引の検証」に参加できます。ただし、マイニングとは違って報酬はなく、完全に無償の運営です。ただし同期といわれる全ブロックダウンロードは、PCの環境により数日〜数週間かかるといわれています。
通常、マイニングノードにはフルノードの機能も含まれていますが、マイニングは利益動機に左右されやすく、その数が減る可能性もあります。そこで、報酬を目的とせずフルノードだけを運営する人や団体の存在が、ビットコインの分散性と耐久性を支えているのです。
フルノード(補足)
フルノードは、マイニングに隠れがちな存在ですが、ネットワークの健全性を保つうえで不可欠です。フルノードも、役割、報酬、コスト、なぜ動かすのか?、存在意義、他通貨との比較という視点で掘り下げることができます。
| 役割 | |
| 報酬 | |
| コスト | |
| なぜ動かすのか? | |
| 存在意義 | |
| 他通貨との比較 |
- 役割:取引やブロックがルールに従っているかを検証し、ブロックチェーン全体のデータを保持します。また、他のノードやウォレットにデータを配布します。データサイズは約680GB(2025-09-11時点)規模です。
- 報酬:マイニングと違い、ビットコインを受け取る仕組みはありません。完全に無償の運営です。
- コスト:24時間稼働のPCやサーバー、データサイズとノードソフトウェアを超えるストレージ、電気代・通信費が必要です。ただし一般的なPCで十分対応できます。
- なぜ動かすのか?
- 自己防衛:自分のウォレット取引を第三者に頼らず検証できる。
- 思想的理由:「ビットコインはみんなで守るもの」という分散思想への共感。
- ビジネス:事業者にとっては必要なインフラで、ユーザーにサービスを提供するために必須。
- 存在意義:マイニングノードにもフルノード機能は含まれますが、マイナー数は利益動機に左右されて増減します。一方、フルノードは報酬に依存しないため、独立して運営され続けることがネットワークの健全性を支える要素になっています。
- 他通貨との比較:フルノードは他の暗号資産にも必要です。しかし、ビットコインはその数が圧倒的に多く、分散性の高さを支える重要な要素となっています。
ハードウェア視点のマイニング
マイニングは、ハードウェアの視点で見ると、2つの形があります。
- マイニングマシン:専用の半導体(ASICなど)を用いた装置で、ブロック生成するマシンであるなら、フルノード機能を持ちますが、ASICマイナー単体ではフルノード機能を持たない場合もあります。
例えばマイニングプールに参加する場合は、多くのマシンは計算部分だけを担当し、フルノード機能はプールが担当します。
- マイニングプール:たくさんの人が持っているマシンの計算力を集めて「チーム」としてマイニングを行う仕組み。ブロックを見つけたら、チームで得た報酬を、それぞれの貢献に応じて分け合います。まるで「みんなで宝探しをして、見つけたら山分けする」イメージです。
- ソロマイニング:一人でマシンを動かしてブロックを探すやり方。もし見つければ報酬を全部ひとり占めできますが、現在は競争が激しく、個人で成功するのは宝くじに当たるくらい難しくなっています。
- 一般のパソコン:市販のPCでもフルノードを構築できます。ブロック生成はできませんが、取引やブロックを検証・保存し、さらにそのデータを他のノードに中継・配布する役割を担っています。これらによりネットワークの分散性と信頼性が支えられています。
ライトノード
ライトノードは、スマートフォンや一般的なパソコンでも動かせる「軽量版のノード」です。
フルノードのようにすべての取引データを保存するのではなく、ブロックの見出し部分(ブロックヘッダー)だけを保持し、必要に応じてフルノードに問い合わせながら取引を確認します。
この仕組みは SPV(Simple Payment Verification:簡易支払い検証) と呼ばれ、実際に多くのウォレットで利用されています。
- メリット:データ容量が小さく、スマホやPCで手軽に利用できる。
- デメリット:最終的な検証はフルノードに依存するため、自分だけで完全に安全を保証できるわけではない。
つまり、ライトノードはフルノードの一部機能を肩代わりするものではなく、「利用のしやすさ」を提供する仕組みです。
フルノードに依存して動作するため、セキュリティ面ではフルノードより劣ります。
ネットワーク全体の健全性や信頼性を支えているのは、あくまでもフルノードの役割なのです。
51%攻撃
「51%攻撃」とは、ビットコインのマイニングにおいて ネットワーク全体の計算能力(ハッシュレート)の過半数を、悪意ある人物や組織が支配すること を指します。
これが実現すると攻撃者は承認される確率が高くなり、自分に有利な形でブロックを作り続けることができます。
具体的には次のような行為が可能になります。
- 自分の送金を取り消し、同じビットコインを二度使う「二重支払い」
- 一時的に正当なブロックの承認を妨害する
- 自分の利益につながるブロックだけを選んで承認する
一方で、誤解してはいけないのは、以下のようなことは 「できない」 という点です。
- 他人の送金を勝手に盗む
- 自分の残高を勝手に増やす
つまり、51%攻撃によって可能になるのは「自分の取引を巻き戻す」「取引を遅らせる」といった限定的な不正にとどまります。とはいえ、システムを破綻させていくには十分です。
フルノードの限界
ここで疑問になるのが「フルノードがたくさんあれば防げるのでは?」という点です。
しかし、51%攻撃は「ルールの範囲内」でチェーンを操作する行為です。形式上は正しいブロックなので、フルノードでは弾けません。
したがって フルノード多数支配=51%攻撃 というのは誤解であり、実際に意味を持つのはマイニングの計算能力の支配です。
なぜ現実的には不可能に近いのか
このように理論的には可能でも、現実には51%攻撃はほぼ不可能です。その理由は以下の通りです。
- ビットコインのハッシュレートは世界規模で膨大
- 過半数を握るには、膨大な台数のマシンと膨大な電気代、サーバ代やメンテナンスが必要
- 攻撃で得られる利益よりもコストが圧倒的に大きい
つまり、「攻撃するより正しくマイニングする方が利益になる」というように、合理的に判断行動しなければならないように設計されているのです。仮に非合理に判断行動しても物理的に不可能な物量です。
そのため51%問題は、完全とはいかないですが、現実をみると解決しているのです。
倫理を超えた信頼性
ビットコインの革新は、「その人物や組織が正しいから信用できる」という倫理的な基準に依存しない点にあります。
たとえ悪意ある人物や組織であっても、システムの設計上、正しくマイニングする方が合理的であり、同じ行動を取らざるを得ません。
つまり、ビットコインは「信用できる人がいるから安全」なのではなく、システム自体が誰であっても正しい行動に収束させるように作られているのです。ここにビットコイン最大の強みがあります。
また、通信の不具合や一部のノードが故障しても、ネットワーク全体の合意形成に大きな支障はありません。
この性質によって、分散システムにおける有名な課題「ビザンチン将軍問題」も実用的に克服しています。
ビザンチン将軍問題とは?
複数の将軍が敵を攻めるために協力する場面を想定した思考実験です。
・将軍たちは通信で作戦を伝え合うが、中には裏切り者が混ざっているかもしれない
・誰が正しい情報を送っているか分からない中で、どうすれば全員が同じ行動に合意できるか?
これが「ビザンチン将軍問題」です。従来のシステムでは、中央の信頼できる司令塔がなければ解決が難しいとされてきました。
ビットコインは Proof of Work(計算競争) と 経済合理性 によって、この問題を現実的に解決しました。つまり「通信システムやノードの故障・事故があっても、悪意ある人物や組織であっても、また裏切り者がいても、全体の合意の形成は壊れない」という仕組みを初めて実現したのです。
分権化
ビットコインのネットワークは、分散された多数の参加者による協力によって維持されており、個人や組織が一方的に操縦したり不正を行ったりするのは困難です。これにより、ビットコインは安全性と信頼性が高く、耐久性のあるシステムとして機能しています。
中心となる管理者や権威者が存在しないため、ビットコインは「高い分権化」を実現しています。さらに、創始者であるサトシ・ナカモトの消息不明という事実が、この分権化のイメージをいっそう強めています。
ウォレットの種類
ビットコインを購入したら、送金・受取・保管するためにウォレットが必要です。このときに使われるのが 公開キー(公開鍵) と 秘密キー(秘密鍵) です。
この2つは 「鍵ペア(キー・ペア / Key Pair)」 と呼ばれます。
鍵ペア(キー・ペア / Key Pair)
公開鍵と秘密鍵を組み合わせたものです。
- 公開キー(アドレス)
他人に教えても問題なく、ビットコインを受け取るための「宛先」として利用されます。
→ メールでいう「メールアドレス」のような役割で、受け取り用です。見せてもOK。 - 秘密キー(秘密鍵)
ビットコインを動かす(送金する)ときに必要な「本人だけが持つ鍵」です。
→ メールでいう「パスワード」のような役割
秘密鍵があれば誰でもそのビットコインを動かせてしまうため、絶対に他人に知られてはいけません。
ウォレット
鍵ペアを管理するためのソフトやデバイスのことです。
ウォレットにはホットウォレット(オンライン)とコールドウォレット(オフライン)の2種類があります。ホットウォレットはインターネットに接続されており、便利ですがセキュリティ面でのリスクがあります。
一方、コールドウォレットはオフラインで保管されるため、セキュリティが高いとされています。
より絶対のセキュリティーを求めるならペーパーウォレットという方法もあります。
| 種類 | 機能 |
|---|---|
| ホットウォレット | インターネットに接続されたオンライン状態のウェブウォレットになります。これは取引所のウォレットやモバイルウォレットアプリになります。 そのモバイルウォレットアプリには、Trust Wallet(トラストウォレット)などがあります。 |
| ハードウェアウォレット | ハードウェアウォレットは、暗号通貨を外部に保管するための専用デバイスです。最大の特徴は、送金や受取時に必要な秘密鍵をデバイス内部でオフライン管理することにあります。 取引の署名を行うときだけオンラインに接続しますが、秘密鍵そのものは外部に出ないため、高いセキュリティを保てます。 代表的な製品には Ledger Nanoシリーズ や Trezor があります。 |
| ペーパーウォレット | ペーパーウォレットは、暗号通貨の公開鍵と秘密鍵を印刷した紙を使用しています。 印刷された紙をインターネットから切り離して保管することでセキュリティを確保します。 |
| Lightning Network対応ウォレット | 他のウォレットとは違い、ビットコインの即時・少額決済向きにするウォレットです。 |
Lightning Network対応ウォレット
ビットコインブロックチェーンを使用した第二のネットワークである、Lightning Network(L2)を使用して、ビットコインを即時・少額決済向きにするウォレットです。
残念ながら、日本では普及していません。
簡単にいうと、日本円の1円未満のビットコインをサトシ(satoshi)という分かりやすい単位を使用し、少額の支払いや即時送金が可能になるウォレットです。
✅ Lightning対応ウォレットの特徴
このウォレットにより、普通の小銭を使う感覚でビットコインが使えます。通常のビットコインの取引より高速かつ手数料が激安(ゼロ〜数円)で、コンテンツ課金や投げ銭、ゲーム報酬、音楽ストリーミングなど日常利用向けになります。
単位は、サトシ(satoshi)になります。1サトシ(1 satoshi)は 0.00000001 BTC に相当し、ビットコインで扱える最小単位です。
ビットコインの価格が1BTC=1,000万円の場合、1 satoshi はおよそ0.1円となり、日常的な少額決済にも対応できます。これなら日本では、1BTCが1億円になるまでは、問題なく使えることになります。
たとえば、
0.000043 BTC と表記するより、4,300 satoshi と表した方が、視覚的にもわかりやすく、直感的に金額のイメージがしやすいということです。
しかし将来的に、ビットコインの価格がさらに高騰して 1BTC=10億円 を超えるようになると、1 satoshi = 10円 という水準になります。日本で1000円の物が、100satoshiになります。1円は、0.1 satoshiになり、分割不能になります。このように、ビットコインが高額になると、1 satoshiでさえ「高額」になっていき、日常の少額決済がしづらくなります。結果として、1satoshiも高額決済専用通貨扱いになっていく可能性があります。
この問題の根本には、ビットコインの仕様が関係しています。
ビットコインは設計上、小数点以下 8桁まで(= 1 satoshi = 0.00000001 BTC)が最小単位で、それ以下(例:0.1 satoshi)は扱えません。
ただし Lightning Network では、さらに細かい msat(ミリサトシ:1/1000 satoshi) という単位が導入されており、ウォレット内部ではこの msat を使って計算されています。
そのため、ユーザーは「小数 satoshi」を送金できるように見え、少額決済でも問題なく利用できる仕組みになっています。
しかし価格変動が大きい以上、決済通貨としての普及には限界があり、現状はステーブルコインが主に使われています。
✅おすすめのLightning対応ウォレット
Wallet of Satoshi :登録不要・日本語対応・スマホ完結・初心者でも使いやすいようです。
他にもあるようですが、より専門的です。
satoshiによる日常の支払いは、海外では普及し始めているようですが、日本での普及度は限定的です。しかし、より技術が安定して、市場で受け入れられるようになれば、普及していくかもしれません。
ビットコインを始めるための手順
ビットコインを始めるには、取引所で売り買いできるようにします。それには、いくつかの手順が必要です。以下では、ビットコインを始めるための基本的な手順について解説します。
アカウント作成
ビットコインを購入する際は、まず取引所を選ぶことから始めます。次に、その取引所で口座を開設し、最後に本人確認(KYC)手続きを行えば準備完了です。
取引所の選択
まず、ビットコインを売買するために取引所を選択します。取引所は多種多様であり、日本の有名な取引所には、Binance Japan、bitFlyer、Coincheck、GMOコインなどがあります。
取引所を選ぶ際には、最低取引金額や手数料、取り扱う通貨の種類、セキュリティなどサービスの内容が異なりますので考慮してください。
自分に合った取引所を選びましょう。
口座を開設
選んだ取引所のウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成します。通常、メールアドレスや電話番号、本人確認書類の提出が必要です。
本人確認
取引所がKYC(Know Your Customer)プロセスを実施している場合、本人確認書類(パスポート、運転免許証など)の提出が必要です。
これにより、取引所はあなたの身元を確認します。
これで承認されればビットコインの取引ができるようになります。
ビットコインの購入
次に、ビットコインを購入するための準備を行います。
まずは取引所のインターフェースや手数料、入金方法を確認し、円をビットコインに交換する取引を行いましょう。
その後、資産を安全に保管するためのウォレットを準備します。さらに、利益を確定させるタイミングや損失を抑える仕組みを考えながら、計画的に運用することが大切です。
入金
取引所に資金を入金します。
クレジットカード、銀行振込、暗号通貨の送金など、入金方法は個人によって異なります。これらの手順を踏むことで、ビットコインを趣味として始める準備が整います。
取引
入金が確認されたら、取引所の取引画面から希望の暗号通貨ペア(BTC/JPY)を選択し、売買注文を行います。
市場価格で即座に取引することもできますし、指値注文を設定して特定の価格で取引することもできます。
先ずはデモで慣れることをお勧めします。
保管
取引が完了したら、取引所に残っている暗号通貨を適切に保管することを考える必要があります。セキュリティの観点から、取引所ウォレットにすべて入れておくのではなく、個別のウォレットに送金して保管しておくことをお勧めします。
しかし、だからといって取引所ウォレットを使用しないで、個別の暗号通貨ウォレットで取引するごとに送金していると、手数料がかかりマイナスになります。いくらかは取引所ウォレットに残すのが賢明です。とはいえ、どのくらい残すかは個人の判断になります。
利益の確定と損失の制限
取引を行う際には、利益を確定させる目標を設定し、損失を抑えるための売値を設定することが重要です。
取引所の利用にはリスクが伴いますので、資金管理には十分な注意を払い、慎重に取引してください。
ビットコインの趣味としての楽しみ方
ビットコインを趣味とするなら、現物の長期保有一択です。でも遊びとして、「回転」という方法があります。そして、降下と低値が長期続き不安になっても、全ビットコインを売らないようにする「強い意志」も必要です。これら3つによって、ビットコインを趣味として楽しむことができます。
現物の長期保有一択
ビットコインの価格は日々変動します。デイトレードやスイングトレードといった取引を行うことで、その価格変動を利用して利益を上げることができます。
しかし、リスクも高いため注意が必要です。とはいえ、そんなリスクを負う必要はありません。何故ならビットコインは趣味だからです。
したがって長期保有の現物一択です。投資としてもシンプルです。
金投資と変わりません。
長期保有としての投資
ビットコインの長期保有は、一番シンプルな投資であり、将来のビットコイン価格の上昇に期待して保有することが目的です。
とはいえ、ただ保有はつまらないかもしれません。
であるなら、一部だけ現物の売り買いをして、BTCを増やしていくのはどうでしょうか。いうなれば、ビットコインコレクターです。つまり、0.25BTCを0.5BTCのようにしていくのです。これを「回転」運用と言います。
回転
単純に現物の一部を上がったら売って、下がったら買うを繰り返して、コツコツとBTCを増やしていくのです。
実際にやってみると手数料もかかるのでなかなか難しいところです。
下はBB指標による「売り買い」のタイミングのイメージ画になります。

それでも現物なので、例え暴落しても、また上がっていくのを待つだけでよいので気が楽です。ビットコインのここが、他の暗号通貨と違うところです。
高値で売る時のタイミング(利確)と、最も購入したいタイミングである「底値」の見極めは難しいですが、そこはチャート慣れしていくしかないでしょう。
実際、上がって下がっての繰り返しなのだから、時が解決してくれます。
焦らないのが肝心です。
そして、決して他のトレードで取引を行ってはいけません。
趣味の範疇ではなくなって直ぐに破産する可能性もあるからです。
強い意志
降下と低値が長期続き、不安に駆られて焦っても、ビットコインを「強い意志」で売らないようにします。この意志の力を暗号通貨界では「握力」と言ったりします。そして、売らないことをガチホールド、略して「ガチホ」と言ったりもします。
そして強く握ってガチホしていられる根拠が、ビットコインに関しての知識です。「ビットコインは資産として十分に信用できる」と思える知識があれば、握力が強くなり、ガチホしていられるということです。そういった知識を「追う・知る」もビットコインが趣味として楽しめる理由です。
その知る方法は、上記の技術や世界観をより掘り下げ考察していくことです。更に、より強力な握力のために、ネット上の情報を調べたり、コミュニティに参加し情報の交換をするのも良いでしょう。
ビットコインは世界情勢とリンクしていて変動もありますが、ネットワークとコンピュータが存在する社会では、トップクラスに信用における資産と分かると思います。どんな世界に行ってもネットワークで「価値を証明」できるのが強みです。その裏で価値を支えているのが、コンピュータによる計算力と検証、電力という物理世界になります。
ビットコイン関連のコミュニティ参加
ビットコインを趣味として始めるなら、ビットコイン関連のネットコミュニティに参加することもおすすめです。
そこでは他のビットコイン愛好家と交流し、情報交換やディスカッションを楽しむことができます。
ビットコインは「知名度」「資産」「技術」「独特な世界観」という4つの側面を持ち、投資対象としてだけでなく、趣味としても楽しめる魅力があります。
そのため、基礎知識や取引の始め方の手順、そして趣味としての楽しみ方を知っておくことで、より深く味わうことができるでしょう。
- ビットコインの魅力
- 世界的な普及と注目度の高さ
- 投資としての値動きの可能性
- ブロックチェーンという先端技術への興味
- サトシ・ナカモトや価格変動にまつわる謎と世界観
- 基礎知識
- 通貨単位は「BTC」
- 2009年にソフトウェアが公開され、世界中に拡大
- ブロックチェーン、マイニング、フルノードにより分散的に運営
- 利用には「ウォレット」が必須
- 51%攻撃とビサンチン将軍問題を解決
- 始め方の基本手順
- 取引所を選ぶ
- 口座開設と本人確認(KYC)
- 入金して購入
- 資産をウォレットに保管
- 趣味としての楽しみ方
- 現物の長期保有が基本
- 回転取引で少しずつBTCを増やすのも一案
- 知識を深め、コミュニティに参加して楽しむ
- 長期下落時にも強い意志(握力という)を保ち、焦らず構える(ガチホ)
ビットコインには魅力があり、世界情勢やテクノロジーと深く結びついた資産です。
資産形成であるなら、ある程度まとまった資金が必要になりますが、趣味として体験する程度なら、小額からでも気軽に始められます。趣味として始めたことが、新しい発見や学び、世界とのつながりを感じられるはずです。
ビットコイン|Q&A

趣味として始めるビットコイン入門ガイド|まとめ
ビットコインを始める際には、基礎知識の習得や取引所での口座開設、ウォレットの設定などの手順が必要です。
ビットコインは投資としても興味深いものであり、価格の変動によるトレードや長期保有などさまざまな活用法があります。
また、ビットコイン関連のコミュニティに参加することで、他の愛好家と交流し情報を共有することもできます。
ビットコインの世界は常に変化しており、リスクも伴いますが、その魅力に惹かれる多くの人々が参加しています。自己責任で取引を行い、楽しみながらビットコインの世界を探求してみてください。
以上で、ビットコインを趣味として始めるための基本的な手順や活用法についての解説を終えます。趣味で始めるとはいえ、ビットコインを始める際には、常に情報を吟味し、慎重に行動することをお勧めします。
本記事は、ビットコインやミームコイン・魔界コインの実際の取引経験、Pow時代のイーサリアムマイニング経験、ネット上の情報をもとに構成しています。
※本文では、ビットコイン・ミーム・魔界コインの取引経験、イーサリアムのマイニングについての詳細な記述は行っていませんが、背景知識として活用しています
更に本記事は情報提供を目的とした一般解説であり、投資助言ではありません。暗号資産の取引は価格変動リスクが高いため、最終判断は自己責任でお願いします。 また税制は変わり得るため、最新の税務情報の確認もしてください。