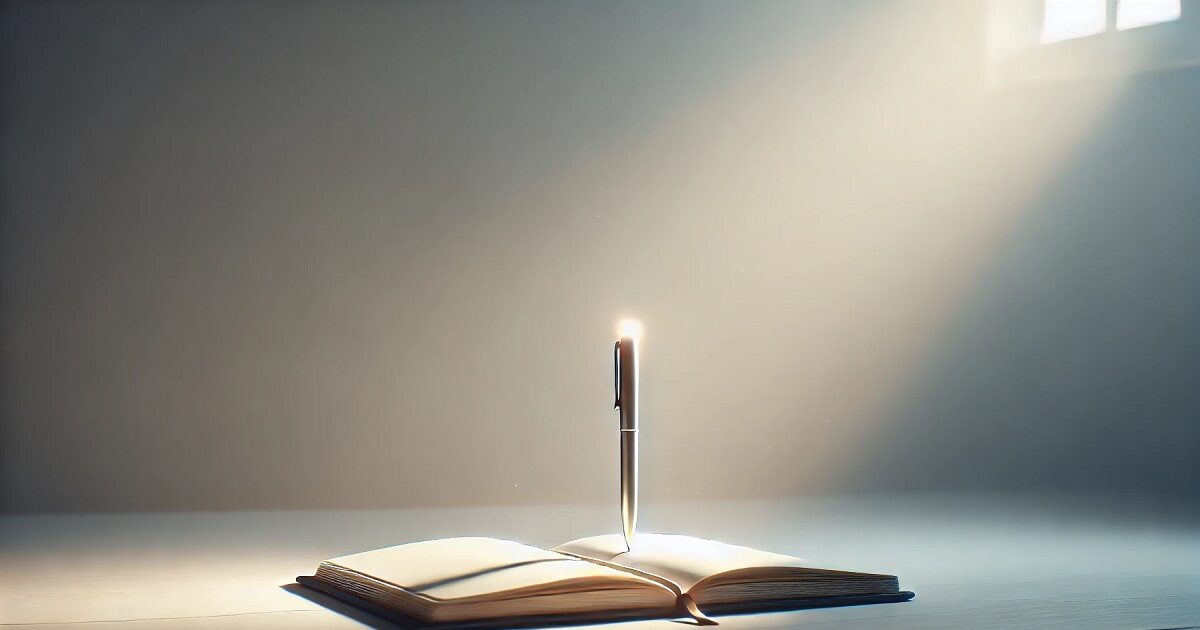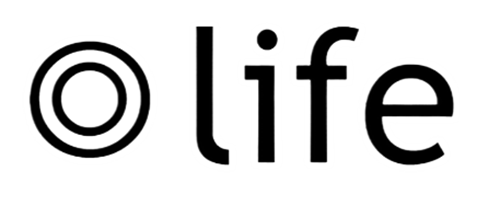好きなことや興味を記事にすることで、誰かと共感し合ったり、新たな視点を得ることができます。
「自分の考えを発信したい」「文章を通じて何かを伝えたい」と思ったことはありませんか?
しかし、「記事を書くきっかけがない」「何をどう書けばいいのか分からない」と感じている方も多いでしょう。
そこで、本記事では、初心者でも簡単に記事作成を始められる手順を解説します。
記事を書くことは単なる趣味ではなく、自己表現の一つの手段であり、実用的なスキルにもなります。
実際に、記事を書くスキルはメールやレポート、コンテンツ制作に必要な台本作りなど、さまざまな場面で役立ちます。
本記事を読むことで、記事を書くメリットや作成手順、コツを学び、自分なりの発信を始めることができるでしょう。
さらに、記事を掲載する媒体や、記事作成を仕事にする方法についても触れます。
「好きなことを形にしたい」と思う人向けにまとめました。
参考にしてください。
- 記事を書くことで得られる4つのこと。
- 記事作成のための3つのポイントや手順と各種手法。
- 記事を載せる媒体について。
- 記事を主な業務としている職種。
記事を書くことで得られること
記事で得られることは4つです。
- 自己満足感:記事を書くことは、自分の興味や情熱を形にしやすい自己表現の手段です。
言葉にする過程で思考が整理され、自己理解が深まると同時に成長も実感できます。
そのため、書くこと自体が大きな満足感をもたらします。 - 手軽に始められる表現手段:誰でも手軽に始められる自己表現の方法の一つです。
ブログやSNSなどのプラットフォームを活用すれば、簡単に自分の考えを発信できます。
継続していくことで表現力が磨かれ、より伝わりやすい文章が書けるようになり、自分の考えや思いを効果的に届けられるようになります。 - 共感と交流を生む:記事を通じて、自分と同じ興味・関心を持つ人々とつながることができます。
経験や考えを共有することで共感が生まれ、新たな友人やコミュニティの形成につながることもあります。 - 新たな視点やアイデアの獲得:記事を書くことは、新たな視点やアイデアを得る絶好の機会です。
読者からのフィードバックやコメントを通じて、多様な意見に触れることで、自分では思いつかなかった考えや知識を得ることができます。
視野も広がり、より深い洞察を持つことができるようになります。
記事作成ポイント
記事を書く際の読者の関心を引く3つの工夫。
- ユニークな視点:好きなことや興味を記事にする際には、自分の好みを考慮したユニークな視点や独自のアプローチを取り入れることです。
他の人とは異なる視点からテーマを掘り下げることで、読者の興味を引きつけることができます。 - タイトルと見出しの作成:記事を書く際には、興味を引くタイトルや見出しを工夫することが重要です。
タイトルや見出しには具体的で興味を引くキーワードを使用し、読者に興味を持たせるようにします。 - 情熱を伝える表現方法:記事にする際には、情熱を伝える表現方法を工夫することも必要です。
具体的な経験や感情を文章に込めることで、読者に自身の情熱や興味を伝えることができます。
記事作成手順
始め方とその後に取り入れたい各手法です。
記事作成手順
記事を書くには、以下の手順で始めます。
文章を書き始める際は、まず簡潔でシンプルな内容にしましょう。
複雑なテーマや深い考察よりも、身近な話題や自身の経験に基づいた内容を選ぶことで、スムーズに書き進めやすくなります。
その方が自然にアイデアが生まれ、無理なく文章を組み立てられます。
初めて文章を書く人にとっては、自分が思っていることを表現することも必要です。
自分の感情や考えを自由に書き出すことで、文章作成のハードルを下げることができます。
無理に他人の期待に応えようとせず、自分らしさを大切にしましょう。
文章を書く前に、プランニングやアウトラインを作成することも重要です。
書くべきポイントや順序を整理することで、スムーズに書き始められます。
また、何から書けばよいかが明確になり、迷わず文章を構築できるようになります。
- プランニング:何を書くかを計画すること。
- アウトライン:概要を書き出すこと。
文章の骨子となるポイントや順番をまとめること。
書き始める際には、フリーライティングという方法が役立ちます。
フリーライティングでは、特定のテーマについて制限時間内に自由に書き続けることで、アイデアを出しやすくなります。
完璧な文章を書くことよりも、まずは自由に書くことに集中しましょう。
この方法は緊張せずに文章を書き始めるのに適しています。
今後に必要と感じる文章の作成技法は、実践とフィードバック(読者の)を重ねながら使用していきます。
これらのポイントを意識することで、文章を書くことが始めやすくなります。
先ずは、自分のペースで少しずつ慣れていくことです。
代表的な文章の作成手法と全体の構成法
作成手法と全体の構成法とわけて解説します。
記事を効果的に書くためには、全体の構成を考えたうえで、具体的な作成手法を組み合わせることです。
作成手法
記事を書く際には、読者に伝わりやすい工夫を取り入れることが重要です。
以下の手法を活用すると、効果的な文章が作成できます。
- ストーリーテリング: 読者の関心を引くために、ストーリーテリングを使用します。
興味深いエピソードや実体験を取り入れることで、読者の心に訴えかけることができます。 - 引用やアナロジーの使用: 有名な引用やアナロジーを使用することで、読者に説得力を持ったメッセージを伝えることができます。
- 具体的な例:抽象的な概念や理論を具体的な例や事実に基づいて説明することで、読者が理解しやすくなります。
- リストや箇条書き:複雑な情報を整理しやすくするために、リストや箇条書きを使用します。
読み手に重要なポイントをわかりやすく提示することができます。 - 問いかけ:読者に参加を促すために、問いかけを使用します。
読者に自分自身の意見や経験を考えさせることができます。 - 5WH1:意味は、Who (誰)What (何)When (いつ)Where (どこ)Why (なぜ)How (どのように)になります。
これらの要素を考慮することで、記事や報告書の内容が読み手にとってわかりやすく、完全に情報が伝わるようになります。
構成法
以下の技法を活用して、記事を構築しましょう。
記事全体の流れが整理され、読みやすく分かりやすくなります。
- PREP法(Point, Reason, Example, Point):ビジネス記事やブログ記事、短い記事などの説明的な文章に適しています。
- Point(結論):最初に結論を述べる。
- Reason(理由):結論の理由を説明する。
- Example(具体例):具体的な事例を示す。
- Point(再結論):最後に再度結論を述べ、理解を深める。
- SDS法(Summary, Details, Summary):プレゼンやレポート記事、説明文に向いています。街頭演説にも使えます。
- Summary(概要):記事全体の要点を簡単に述べる
- Details(詳細):具体的な説明やデータを提供する
- Summary(まとめ):最後に内容をまとめ、読者に印象を残す
- 起承転結:物語やエッセイ、コラムなどに適しています。
- 起:テーマや問題提起を述べる。
- 承:その内容を深掘りする。
- 転:意外性や新しい視点を加える。
- 結:結論としてまとめる。
- 序論・本論・結論(序本結):論理的な記事や解説記事、レポートに向いています。
- 序論:導入部分でテーマや背景を説明する。
- 本論:記事の中心となる内容を詳しく説明する。
- 結論:記事のまとめや主張を再確認し、読者にアクションを促す。
これらの手法を組み合わせることで、より魅力的で効果的な文章を作成することができます。
記事を載せる媒体

記事を載せる媒体にはさまざまなものがありますが、主なものを以下に挙げます。
- 新聞:一般紙や専門紙などで記事が掲載されます。
地域新聞や全国紙など、さまざまな種類があります。 - 雑誌:一般誌や専門誌など、様々なジャンルの雑誌で記事が掲載されます。
ファッション、健康、趣味などさまざまなテーマの雑誌があります。 - ウェブサイト:オンラインメディアやブログなどのウェブサイトで記事が公開されます。
ニュースサイト、専門サイト、個人ブログなどがあります。 - ソーシャルメディア:Facebook、X、InstagramなどのSNSで記事が共有されます。
短い記事や画像付きの記事などが主流です。 - 企業のウェブサイト: 企業や団体のウェブサイトで、会社案内や製品情報、ブログ記事などが公開されます。
企業のPRや情報発信のために活用されます。
これらの媒体は、それぞれ異なる読者層や情報発信の形式を持っています。
記事を執筆する際には、対象とする読者や目的に合わせて適切な媒体を選択することが必要です。
記事を仕事としている職種
以上のような媒体で仕事をしている職種があります。
- ライター/ジャーナリスト: 新聞社や雑誌社、オンラインメディアなどで記事を執筆する仕事です。
ニュース記事、特集記事、コラムなどさまざまなジャンルの記事を担当します。 - コンテンツライター:ウェブサイトやブログ、SNSなどのコンテンツを制作する仕事です。
企業や広告代理店、マーケティング会社などで雇用され、SEO対策やコンテンツマーケティングのための記事を制作します。 - ブロガー:自身のブログを運営し、そこで記事を執筆することで収益を得る仕事です。
特定のテーマに特化したブログや雑記ブログなど、さまざまなジャンルがあります。 - コピーライター:広告やマーケティングのためのコピーを制作する仕事です。
商品やサービスの魅力を伝えるための広告文を作成し、企業や広告代理店などで雇用されます。
これらの職種では、文章を書く能力やコンテンツの企画力、情報収集能力などが求められます。
また、柔軟な発想や想像力も必要です。
質問
Q:5WH1だけは基本として気にしていたほうがよいですか?
A:5W1HのWho (誰)、What (何)、When (いつ)、Where (どこ)、Why (なぜ)、How (どのように)は、情報を整理し、読者にとって理解しやすい文章を作成するための基本的な手法です。
これらの要素を考慮することで、記事や文章の論理的な構造を確立し、情報の欠落を防ぐことができます。
特に、情報を提供する際に必要な基本的な要素を網羅するためには役立ちます。
ただし、5W1Hだけにこだわる必要はありません。
他の文章作成のテクニックやスタイルも重要です。
5W1Hを基本として意識しつつも、ストーリーテリングや引用、具体的な例、リストや箇条書き、問いかけなど、さまざまな作成手法を使って文章を豊かにしていくことが大切です。
経験を積みながら、バランスよくこれらの要素を組み合わせて文章を構築していくと良いでしょう。
Q: 記事の長さはどの程度が適切ですか?
A: 記事の適切な長さは、その内容や掲載するメディアによって異なります。
一般的には、ウェブ記事では500〜2000語程度が適切とされますが、ニュース記事やブログ記事などによってはさらに短い場合もあります。
一方、雑誌や専門誌などの印刷媒体では、数千語から数万語に及ぶ記事もあります。
Q:単行本の活字は記事か?
A.一般的には、単行本の活字は「記事」とは呼びません。
記事は通常、新聞や雑誌、ウェブサイトなどのメディアに掲載される短い文章を指します。
これに対して、単行本は一つのテーマや物語をより長い形式で展開するものであり、単行本に掲載される文章は一般的に「章」と呼ばれます。
ただし、単行本の中には、新聞や雑誌に掲載された短い記事をまとめたものや、ブログなどで発表された短いエッセイを収録したものもあります。
このような場合、それらの短い文章を「記事」と呼ぶこともありますが、単行本全体を指して「記事」と呼ぶことは一般的ではありません。
まとめ
当記事は、テーマの選び方から構成の考え方、書き進めるコツまで、実践しやすい方法を解説しました。
記事を書くことは、文章力や思考力が鍛えられ、仕事にも活かせるスキルになります。
後半ではブログやSNSなど、記事を発信するさまざまな媒体についても紹介しました。
また、記事を書くことを仕事にする道もあり、ライターやブロガーなどの職種についても触れました。
記事は、好きなことや興味を具体的に表現できる手段であり、自分の考えを整理し視点を広げます。
また、読者との交流の機会があれば、新たな気づきも得られるでしょう。
まずは身近なテーマから書き始め、少しずつ積み重ねていけば、記事作成の楽しさや意義を実感できるでしょう。
今すぐ、最初の一記事目に踏み出してみましょう!